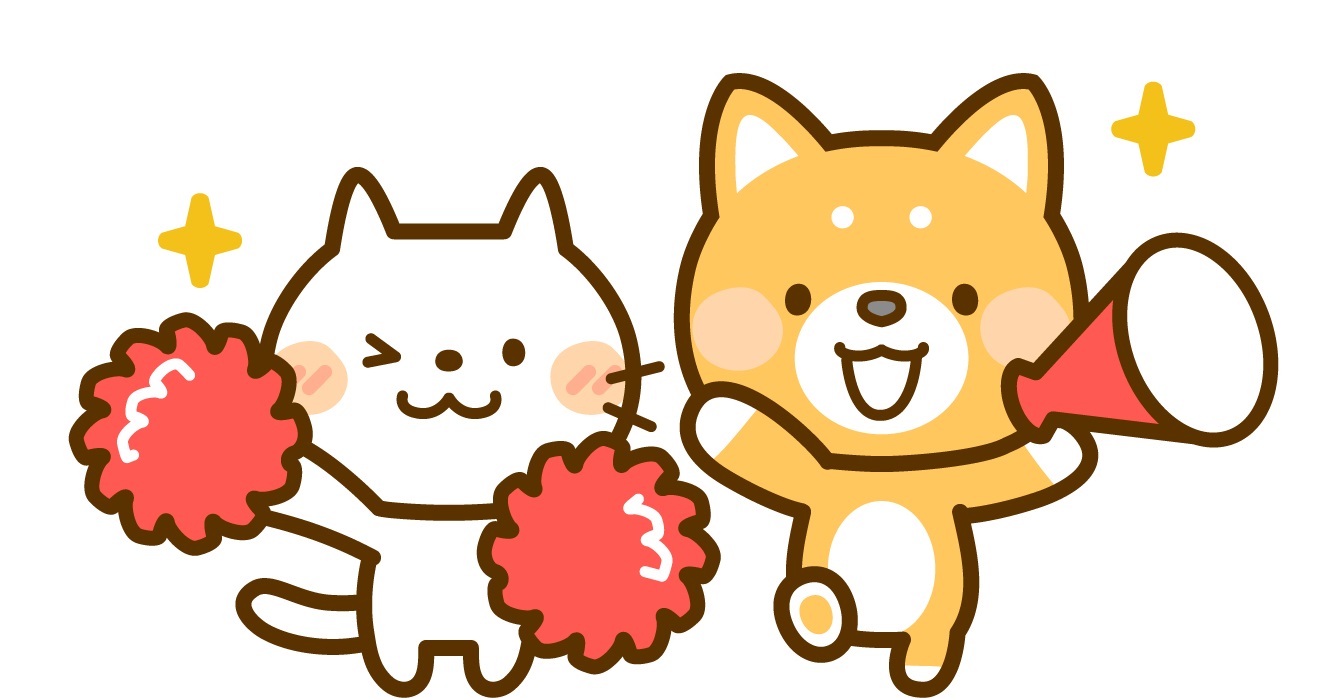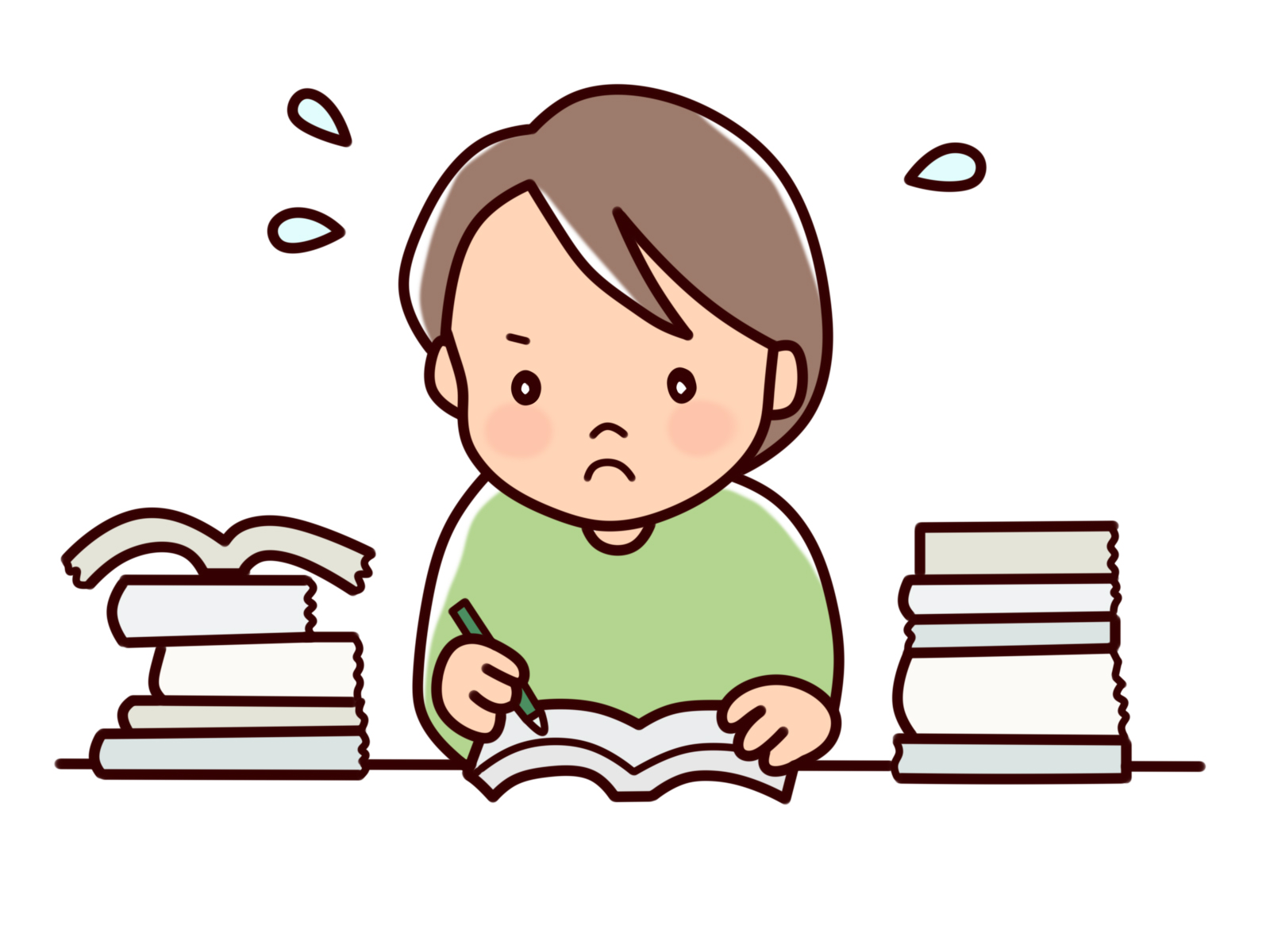こんにちは。四谷学院保育士講座の野本です。
保育士試験の問題は、「児童家庭福祉」「社会福祉」などの科目名を見ても分かるように、法律にかかわる問題が多く出題されているんです。
そもそも「児童」の定義とか、保育所などの「児童福祉施設」の職員の要件や設置人数の条件など、さまざまなことが法律・法令で定められていて、その内容が保育士試験でも出題されます。
法律の改正が、試験勉強に大きく影響するんです。
この記事では、平成29年後期試験を受験される方に向けて、出題範囲と法改正の影響を解説します。
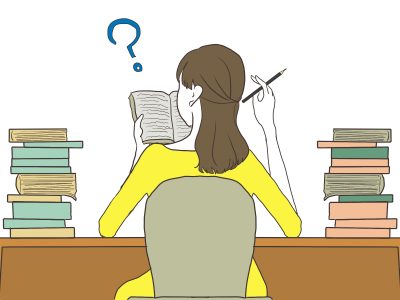
平成29年後期の出題範囲
■筆記試験における法令等については、平成29年4月1日以前に施行されたものに基づいて出題します。
※「平成29年保育士試験 出願申請の手引き[後期用]」P28より
これから筆記試験の勉強をする場合、法改正が無視できません。
前期試験は平成28年4月1日までの情報の中から出題されていましたが、後期試験は平成29年4月1日までに施行された法令等からの出題と確定したからです。
統計などの方法も、もちろん最新情報からの出題となります。
同じ年に行われる試験ですが、前期と後期では出題範囲が違います。注意しましょう。
改正の目玉は「児童福祉法」
今回の目玉は「児童福祉法」の改正です。
平成28年6月に改正されましたから、今後の試験では新たに出題範囲になります。
改正の意図として大きいのはざっくり言うと次の2つです。
・子どもの権利などを「児童福祉法」の理念に明記したこと
・虐待対策(発生予防、発生時の対応、被虐待児の自立支援)の強化
試験に与える影響は?
どんな風に、問題が変わってしまうでしょうか?
実際の出題問題で説明します。
(※H22 児童家庭福祉 問4)
次の文は、「児童福祉法」第1条の記述である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
第1項( A )は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
第2項すべて( B )は、ひとしくその( C )を保障され、愛護されなければならない。
ここで扱われている「児童福祉法第1条」は、ほかの年にも形を変えて出題されてる、いわゆる頻出問題です。
改正により、第1条が次のように変わることになります。
第一条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
文言がちょっと変わるどころではなく、第1項、第2項というくくりも消えています。もちろん、改正前の過去問題をそのまま勉強するのは無意味になってしまいます。
改正されたことはもちろん、改正後の内容をきちんと把握していないと解けないんです。
対策方法は?
「変更点を、一つひとつ全部勉強しないといけない?」
「法律を、全部読みなおさないとダメ?」
答えはもちろん「NO」。安心してくださいね。
「保育士試験」はあくまで保育士になるための試験。法律の専門家ではありません。
そこで、「保育士になる人にとって大事なことは何か」というフィルターをかけて勉強しましょう。
四谷学院では以下のこともあわせて、受講生の皆さんに改正情報を提供しています。
押さえておきたいこと
- ・なぜ今回の変更がされているのか?
- ・変更点のうち、特にポイントとなるのはどこか?
忙しい中、保育士資格のために勉強をしている人の中で、「ザッと目を通す」だけで何が大事なのかわかる人って何人いるのでしょうか?
いくら「保育士にとって大事なところだけやれば、全部やらなくていいですよ」と言っても「その大事なところがワカラナイのじゃ!」という方は決して少なくありません。

そういう場合は、試験対策のプロに頼るのが手です。
四谷学院では、不安な法改正についてもしっかりサポートします。
自分だけでは集めにくい最新の統計情報や通知についても、お知らせ。
プロのサポートを活用して、合格を手にしてください。
詳しくはこちらでご確認ください。
四谷学院 保育士講座ホームページ
このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。
四谷学院は通信講座ですが、あなた専門のサポートスタッフ『担任の先生』がつくようになっています。それが、私たちです。保育士試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。