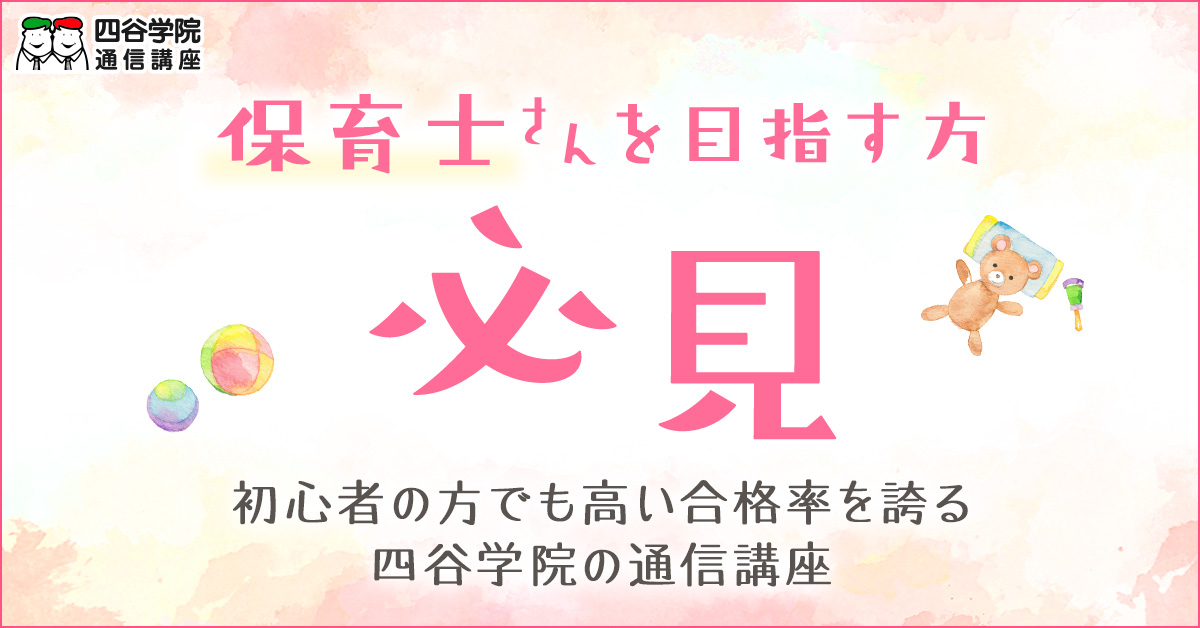こんにちは。四谷学院の野本です。
保育士試験対策を進めていると、様々な「法」を目にしますね。
「日本国憲法」や「児童福祉法」を筆頭に、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(「設備運営基準」)などのように名称に「法」と入っていないものがあったり、「保育所保育指針」も「法」の一種として扱うとされたり、「児童の権利に関する条約」なども「法」としての効力を持つと説明されます。
もちろん「法」はどれも大切なものですが、数多く存在する「法」を全て同列に扱ってしまうと、覚えるものが増えるばかりか、理解も難しくなってしまいます。
ここでは、日本の法体系(日本において「法」がどのように体系づけられているのか)を簡単に整理してみます。
国が制定する法(1):憲法

「法」とは、簡単に言うと、国や地方公共団体が制定するルールのことです。ただ、国会議員や内閣総理大臣、都道府県知事などが、自分の主義・信条に沿って勝手に「法」を制定してよいものではありません。
そこで、「法」を制定する上での基本的なルールとして存在しているものが「憲法」です。「憲法」は国の最高法規であるといわれており、「憲法」の規定は全ての「法」の土台となっています。
ご存じのとおり、日本では「憲法」に当たるものとして「日本国憲法」が存在しており、保育士試験に関連するところでは、第11条の基本的人権の尊重や、第25条の生存権の保障などの規定が、それぞれ関連する「法」の土台となっています。
また、後で解説する「法律」や「命令」は時代の要請に従って何度も改正が重ねられていますが、「日本国憲法」は土台であるがゆえに簡単には改正できない仕組みになっており、現在も改正が行われたことがありません。
土台が揺らげば、それ以外のものが全て崩れ落ちてしまう可能性があるからです。
国が制定する法(2):法律

次に、「憲法」以外の「~法」と名付けられたものを見ていきましょう。「児童福祉法」や「教育基本法」、「児童虐待防止法」など、保育士試験に登場するものだけでもかなりの数がありますね。
これらは「日本国憲法」の考え方に沿って、立法機関である国会(衆議院、参議院)が制定するルールです。これを「法律」といいます。「法律」においては、子ども関連、障がい者関連、高齢者関連、教育関連、虐待関連など、各ジャンルに分けて、国としてどういう対応をとっていくのか、という政策の方向性が示されています。
個々の問題は社会情勢によって変化するため、ニーズが生じれば、政策の方向性を変えるため、新たな「法律」を制定したり、現に存在する「法律」を改正したりしていくことになります。「児童福祉法」が頻繁に改正されるのも、そういったニーズの変化によるものですね。
国会を構成する国会議員(衆議院議員、参議院議員)は、国民の投票によって選ばれた存在であり、その人たちが話し合いによって制定したものが「法律」であることから、「法律」は「憲法」の次に位置付けられています。
国が制定する法(3):命令

「法律」の次に位置付けられるのが「命令」と呼ばれるものです。「命令」は国会での話し合いを経ずに制定することができる「法」であるため、「法律」に比べて迅速かつ機動的に運用することができます。
「命令」には、内閣が制定する「政令」、内閣府(こども家庭庁などが設けられている機関です)が制定する「内閣府令」、各省(厚生労働省、法務省などが当てはまります)が制定する「省令」に加え、大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、法務大臣などが当てはまります)が一定の事項を国民に周知するために制定する「告示」も含まれます。
たとえば、「設備運営基準」は、このうちの「内閣府令」にあたり、「保育所保育指針」は2008(平成20)年に「告示」化されたされたことで「命令」の仲間入りをすることになりました。
「命令」は「法律」に沿って制定されるものではありますが、いずれも国が制定したルールという扱いとなります。
たとえば、「設備運営基準」は「児童福祉法」に沿って制定されたものですが、「設備運営基準」で定められたルールを基に、都道府県が各地の実情に合わせた「最低基準」を設けています。
このように日本の法体系は、「日本国憲法」という共通する考え方を基にして、より具体的な「法律」や「命令」が制定されていく、という形をとっているのです。
まとめ図
日本の法体系をまとめるとこんな感じです。

国際的な取り決め:条約

一方、これらの法体系とは少し違った位置にあるのが、「児童の権利に関する条約」や「障害者の権利に関する条約」などの「条約」と呼ばれる国際的な取り決めです。
保育士試験で出題される「条約」のほとんどは、国連(国際連合)が定めたルールであり、そのルールを受け入れるかどうかについては、各国の判断に委ねられています。ただし、受け入れる際には、そのルールに沿った体制作りが求められます。つまり、「条約」を受け入れることによって、その国の「法」を変えなければならない場合があるのです。
たとえば、「児童の権利に関する条約」で言えば、1989(平成元)年に国連で採択され、日本は1990(平成2)年に署名し、1994(平成6)年に批准しました。
署名の段階では、内閣が「児童の権利に関する条約」で定められたルールに同意しますという表明をしたに過ぎず、その同意について国会の承認を得る、つまり日本国内で「法」の整備ができる段階になって初めて批准となります。
批准により、「条約」も「憲法」とは違った形で、日本国内で「法」を定める上での指針となります。
「こども基本法」第1条では以下のように憲法と児童の権利に関する条約が併記されていますね。
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
このように「条約」も守るべき「法」の一つとみなされることがあるのです。
保育士試験対策の注意点
最後に。内容理解を深めていただくために法体系の紹介をしましたが、保育士試験で「これは法律ですか?命令ですか?」というような出題がされることはまずありません。
あくまで、学習する法律の親子関係を理解するための補助ですのでこの内容を一生懸命覚える必要はありません。それよりは実際の条文に一つでも多く目を通しましょう。
四谷学院通信講座ではどこまで丁寧にやればわからない…という場合はメールで質問を利用していただけます。ぜひ、一人での学習が不安な方はご検討くださいね。

このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。
四谷学院通信講座では、保育士講座専門のサポートスタッフがあなたをサポートします。
保育士試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。