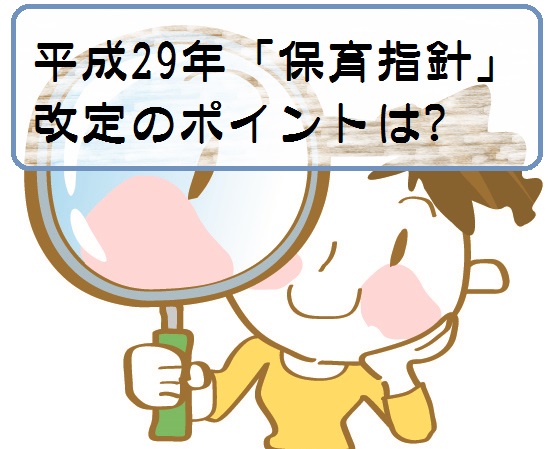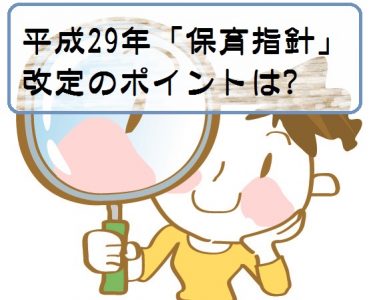
こんにちは。四谷学院の谷村です。
平成30年の保育士試験について、平成30年試験の目玉となる「保育所保育指針」について2回目の解説です。
前回の記事では、保育指針の改定と試験の関係についてお伝えし、さらに「前期試験」を受けることを強くオススメしました。
今回は、具体的に何が変わるのか?をカンタンにご紹介します。
![]() 平成30年保育士試験の目玉!平成29年「保育所保育指針」改定のポイントは?試験対策は?(その1)はこちらから
平成30年保育士試験の目玉!平成29年「保育所保育指針」改定のポイントは?試験対策は?(その1)はこちらから
目次
2017年「保育所保育指針」5つの改定ポイント

改定された新しい保育指針そのものは、2017(平成29)年3月31日に告示されています(でも適用が2018(平成30)年4月1日からなので、試験にはまだ出てきていないのです)。
そして、告示とほぼ同時期に「保育所保育指針の公示について」という通知が厚生労働省から出ています。
この中で改定の方向性として次の5つが示されています。
(2)保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ
(3)子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の記載の見直し
(4)保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性
(5)職員の資質・専門性の向上
前回の記事でお話ししたとおり、「根本となる考え方が180度変わるわけではない」という点が納得していただけると思います。
「保育所保育指針」試験対策として大きな改定ポイントは?

さて、5点の中で特に試験対策上、大きなものが2つあります。
何だと思いますか?
・
・
それは(1)と(2)です。
それぞれ説明しましょう。
<1>3歳未満児の記述がボリュームアップ!

わかりやすい例として、保育所と幼稚園を比べてみましょう。
保育所は3歳未満の子どもが多いというのが特徴的です。幼稚園でもプレ入園などありますが、原則として満3歳以上を預かるのが幼稚園です。
そこで、保育所の特徴として満3歳未満の子どもに対する保育についての記載が充実したのです。
新しい保育指針は全体的にボリュームアップしていますが、この部分が特に大きな要因です。
<2>幼児期の教育を担う機関としての記載が充実!
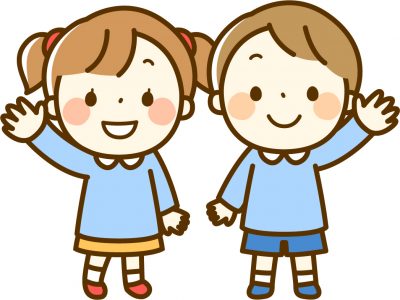
保育所での保育は、単に子どもと遊んでお世話をしているだけではありません。生活や遊びを通じて、幼児期の「教育」を担っています。
この「教育」の部分については、以前から幼稚園に準ずる、言ってしまえば「幼稚園と同じような教育をする」ということになっています。
実はこの「幼稚園の教育」に期待する部分が、同時期に検討されていた学習指導要領(学校でどんな教育をするのかを定めた文書)の改定によって膨らんできました。知識のつめこみではなく、知識を土台にして、問題解決をできる力などがこれからの子どもたちに求められるようになったんです。ニュースや雑誌など記事を目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような流れを受けて、「3つの資質と10の姿」というものが新たに盛り込まれることになります。
試験対策として新たにインプットしなければならない知識ということになります。
まとめ

ここでは、改定内容の一部を取り上げました。そのほかの点についても、従来から強化が進んできたものをさらに充実させています。いずれも、単に暗記するのではなく、どういうことなのかじっくり理解しながら自分の頭で現場への落とし込みを考えることが、よい保育につながりますね。
保育士試験対策としては、新しい保育指針になる前に合格を目指すのが得策です。
その一方、試験に無事通過したあかつきには、保育士として活躍できるよう新しい保育指針も読み込んでいきましょう。
きちんと理解できるから、使える知識が定着します。
くわしくはホームページをご覧ください。
四谷学院 保育士講座ホームページ

このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。
四谷学院は通信講座ですが、あなた専門のサポートスタッフ『担任の先生』がつくようになっています。それが、私たちです。保育士試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。