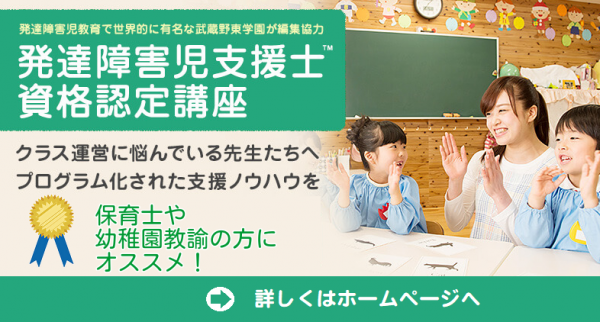こんにちは、四谷学院の石田です。
令和3年後期保育士試験が終わりました。受験された皆さん、本当にお疲れ様でした。
造形分野の令和3年後期の課題について、詳しく解説していきます。
実技試験の「音楽」「言語」は課題があらかじめ発表されていますが、「造形」は当日発表のため、また別の意味で緊張された方も多かったのではないでしょうか?
今回の試験の振り返りとともに、来年の保育士試験を目指される方は試験対策・練習方法などの参考にしてみてくださいね。
目次
当日発表の課題「色水遊び」
当日出題された造形表現の問題文は以下のとおりです。
【事例】
H保育所の4歳児クラスの子どもたちは、園庭で色水遊びをしています。水の感触を楽しみながら、空き容器に色水を入れて並べてみたり、ジュースに見立てたり、色を混ぜるなどして、保育士と一緒に遊んでいます。
2.園庭の色水遊びの様子が分かるように描くこと。
3.子ども3名以上、保育士1名以上を描くこと。
4.枠内全体を色鉛筆で着彩すること。
課題のポイント

今回は色水遊びがテーマでした。
子ども同士や保育士とのやり取りなど、ストーリー設定は特にありませんでした。「色水遊び」と聞いて多くの人がイメージできるような情景がテーマになっています。
事例には、「水の感触を楽しみながら、空き容器に色水を入れて並べてみたり」とあり、道具を使った色水遊びであることがわかります。
また、「ジュースに見立てたり、色を混ぜるなど」と具体的な遊び方も記載されています。
子どもの年齢は4歳
今回は「4歳児クラス」という指定がされました。
例年の様子を考えると、「赤ちゃん」「幼児」「小学生」くらいの区分ができていれば問題ないと思われます。子どもの年齢の描き分けは、それほど厳密ではなく、例年通りと考えてよいでしょう。
4歳児となると、お友達や保育士と一緒に同じように遊んでいる連合遊びが見られるようになる時期でしょう。
色水遊びの様子

上でも述べたように、事例では、
「水の感触を楽しみながら」「ジュースに見立てたり・・・」
とあります。
[条件]には
容器を使って色水遊びを楽しんでいる様子を描くこと。
とあります。
プリンやゼリーなどの入っていた空きカップやペットボトルなど、<容器>を表現することが必須となっており、また「水の感触を楽しむ」という点も表現することが求められています。
色鉛筆で着彩「カラフルな絵」に仕上げるコツ

色水遊びの様子ですから、カラフルなお水を表現した方が多かったのではないでしょうか?
様々な色を使うことで絵の印象を明るくなったと思います。
それ以外にも
バケツなどの道具や子どもたちの服装をカラフルにする
というのが、画面を明るい印象にするテクニックの1つですね。
大小さまざまなコップやカップ、ボウル、ペットボトルなどが描けているとよいでしょう。
水の感触を楽しむために、柔らかい容器やビニール袋を表現される方もいらっしゃったようです。
保育士の様子

今回は、保育士の様子について具体的な指定はありませんでした。
保育士と一緒に楽しく遊ぶ
この部分のみです。
例えば、一緒にしゃがんで水を触っている、ペットボトルをもって近寄る、子どもの肩に手をかけている、横から声をかけている‥‥などなど、色々な表現があるでしょう。
毎回、保育士を表現する際には「何らかの形で子どもにかかわっている様子」を描くことが試験では求められます。今回は自由度の高い指定でした。
子どもたちから少し離れて立っている様子であっても、ニコニコしながら眺めているだけでも、なんとなくやりとりが想像できる絵が描けてれば致命的な失敗ではないと思われます。
子どもは3人以上
人数指定は、例年通りでした。子ども3名、保育士1名を描けば、条件を満たすことができます。
前回と同様に、わかりやすい条件設定でした。
場所は「園庭」
「園庭での色水遊びの様子がわかるように描くこと。」
という条件がありました。
事例には、季節の指定はありませんが、お水を使った遊びですから、暖かい季節かなとは想像できます。
12月に試験が実施されたために、とっさに季節が反応できなかったという感想もありました。色々な季節、テーマを練習していた方にとっては、特に問題なかったかもしれませんね。
以下のようなことが、背景のポイントとなるでしょう。
- 建物の中ではなく「外」である
- 子どもたちが遊ぶのに適切な場所である
- 保育園らしい遊具
- 暖かい季節の昼間
外遊びなので、子ども達には帽子をかぶせるなど、保育士としてのちょっとした配慮が表現できているとよいでしょう。
園庭には木や石でできたテーブルがある園もありますし、敷物を敷いたり、ちょっとした台を置いてジュースを並べたり…
色々と想像が膨らむようなテーマですね。
合格通知の発送日
実技試験結果通知書(合格通知書・一部科目合格通知書)は令和4年1月13日(木)~1月19日(水)の期間に郵送されます。
次回の課題の予想

色水遊びについては、「保育実習理論」の筆記試験でも出題されたこともある、子どもたちに人気の遊びですね。
絵の具を使う色水遊びもあれば、植物の花や葉を使った色水遊びなどもあります。年齢・発達段階によって少しずつアレンジがありますね。
(今回はそこまで詳しい遊びの内容は指定されていませんでした。)
「遊びの発達段階」については、筆記試験対策でも学んだ内容です。
しかし、子どもたちの中には
「友達と一緒に遊ぶことができない」
「いつも一人でいる」
「関わり遊びが苦手」
「言葉でのコミュニケーションが苦手」
こうしたケースも見受けられます。
いわゆる「育ちが気になる子ども」です。
発達障害という診断名がなくとも、少しのフォロー、適切な支援をすることで、子どもの育ちを促すのは、保育のプロ「保育士」の重要な仕事です。
四谷学院では、保育士さん向けの発達障害児支援士資格認定講座を開講しています。
保育士が身につけるべきスキル・知識の1つとしては発達支援は無視できません。
自閉症や発達障害について正しい知識を身につけ、子どもたちの笑顔を守りましょう。
ぜひこの機会に発達障害児支援士についても知っていただきたいと思います。
詳しくはホームページをチェックしてみてくださいね。

このブログは、四谷学院の保育士講座スタッフが書いています。
四谷学院は通信講座ですが、あなた専門のサポートスタッフ『担任の先生』がつくようになっています。それが、私たちです。保育士試験についての専門知識はもちろん、どうしたら迷いなく勉強できるか日々考えているプロフェッショナル集団です。